「民衆が選んでいる」ことが元兇だ


岸田内閣の支持率が20%台から10%台に下落し、もはや支持率恢復の見込みは無いだろう。しかし、我が国の政治が混迷しているのは、岸田文雄が総理大臣になったからではない。日本の“悲劇”は民衆政治に由来する。つまり、民衆が“主体”となって“代議士”を選ぶから、“民衆”が苦しむ結果となってしまうのだ。
各国にはそれぞれ独特な“体質”がある。我が国の歴史を俯瞰(ふかん)すれば、日本の“國體(constitution)”は武士による統治が適切であり、デモクラシーとなれば凋落の道しかない。なぜなら、日本の庶民は被統治能力(governability)に長けているが、統治者(governor)の素質は無いからだ。(註 /「constitution」は「憲法」を意味することもあるが、国家の「体質」指すこともあるので、場合によっては「國體」と訳した方がいい。また、「governability」は「統治される者」の性質を語る言葉なので、「従順な民」とか「統治しやすい国民」という意味をもっている。)
世間のオッちゃんやオバちゃん、兄ちゃん姉ちゃんは、複雑怪奇な政治に興味は無い。ただ、何年かおきに役所から投票用紙が送られてくるので、馴染みの政治家や頼まれた名前に投票するだけ。立候補者の政策立案能力とか政治家の才幹(virtu)なんか、チョコレートのオマケ以下の扱いだ。一般国民にとったら、議員の公約なんてどうでもよく、気になるのは「誰が当選し、誰が落選するか?」の丁半博打だけである。つまり、自分が投票した候補者が当選すれば、「地方交付金をどれだけ持ってくるのかなぁ~?」と予想し、ベテラン議員が落選すれば、暗くなった選挙事務所に興味を示す。そもそも、議員の人格や能力より、“格付け”の方にに好奇心を抱くので、当選した候補者が“反日”でも“売国”でも構わない。選挙が終われば普段の生活に戻ってしまうから、国会の論議なんて馬耳東風だ。自分が選んだ議員の秕政(ひせい)によって苦しんでも、地震や津波と同じ“自然災害”としか思わない。
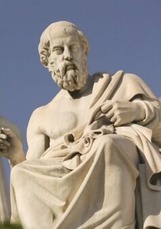 (左 / プラトンの彫像 )
(左 / プラトンの彫像 ) 日本の学校教師は、「アカ」じゃなくても「デモクラシー」を賛美する。しかし、プラトンやアリストテレスのような古代ギリシアの哲学者からすれば、ポリスを崩壊に導く「最低の政治形態」でしかない。学校の先生によれば、真(or善)の統治形態は、君主政と貴族政、穏健な民主政であり、逸脱した政体というのは、僭主政(暴君政)と寡頭政、極端な民衆政であるという。ただし、「多数派の支配」についての説明には、悪意がなくても有害な“チョロマカシ”がある。“善い民衆政体”とは“法”が支配者となる「立憲政(ポリティア/ politeia)」のことで、“悪い民衆政体”とは“烏合の衆”、つまり“暴民(貧乏人)”が主体となる 民衆政(デモクラティア/ demokratia)のことである。
現在の「日本国憲法」というのは、占領軍が押しつけた「マッカーサー憲法」であることは、ご存じの通り。いくら「平和憲法」と呼んでも、その実態は敗戦国(犯罪人)を封じ込めるための“呪文”、ないし“拘束衣”に過ぎない。呆れたことに、高学歴の国民、特に法学部の学生は、憲法を守ることが「法の支配」だと思っているが、こんなのはアメリカ人やイギリス人が考える「法の支配(Rule of Law)」じゃないぞ! (日本の法学者は意図的に慣習法のような歴史的「法(law)」と、議会で制定される「人定法(legislation)」をごちゃ混ぜにして教えているから厄介だ。一般の日本人が口にする「法治主義」は、「制定法(statutes)」至上主義の別名で、場合によっては、國體を否定する人定法だったりする。) 大東亜戦争で“嬲(なぶ)り殺し”の目に遭った日本人は、占領軍から手ひどい“仕置き”を受けてダグラス・マッカーサー元帥に平伏した。しかし、この“属州総督”よりも悪質なのは、「公職追放」で利益を受けた左翼教授であった。
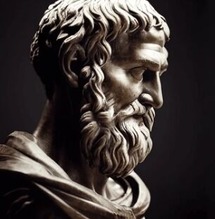 (左 / アリストテレスの彫像)
(左 / アリストテレスの彫像) 日本の皇室や軍隊を憎んだ赤い教授、例えば丸山真男とか大内兵衛、我妻栄、横田喜三郎やその同類と弟子達は、“空席”になった教授職とか学長職に就き、「学問の自由」を錦の御旗にして大学を左翼の牙城に変えていった。そして、占領された東大や京大に入った「元高校生」は、判断力こそ乏しいが、教科書を“暗記”したり、“科挙”の勉強なら得意ときてる。だから、宮沢俊義(みやざわ・としよし)とか芦部信喜(あしべ・のぶよし)、小林直樹(こばやし・なおき)などの憲法学を拝聴すると、何か“高級な世界”に触れたと勘違いし、学費をドブに捨てたと気づかずに感動してしまうのだ。彼らは疑うこともなく“信者”となり、卒業する頃には元気いっぱいのクルクルパーとなってしまう。「国民主権」なんてプラトンやアリストテレスが聞いたら腰を抜かして驚くが、敗戦後の日本人は有り難く思っている。アリストテレスはプラトンほど王政を賛美しなかったが、いやしくも、善き国家なら、究極の主権者は法であり、人間ではない、と主張していた。(George H. Sabine, A History of Political Theory, London : George G. Harrap & Co., 1937, p.91.)
「庶民院」じゃなく「士族院」
日本の政治が長きに亙って混迷しているのは、指導者層なきデモクラシーに拘泥し、商人や買弁から代議士を選んでいるからだ。日本は江戸時代の頃から“民意”の力が強く、幕府や領主は庶民の意向を気にすることが多かったから、民衆から選ばれる民選議員など不必要で、「代官(おカミ)にお任せ!」というのが日本人の考えである。進歩的文化人やマルキスト学者は、封建制を親の敵(かたき)みたいに罵っていたが、明治の頃くらいまでは、支配者の武士的為政者が大衆に媚びるような“デマゴーグ”ではなかったし、外国の手先になる“売国奴”も稀だったから、比較的“健全な社会”であったと言えよう。
(左 / 柴五郎)
武家の躾は些細なことでも平民とは違っている。例えば、会津藩士の家庭に生まれた柴五郎大将は、典型的な武士の躾を受けていた。柴五郎中佐は義和団の乱が勃発した時、その功績で一躍有名になった駐在武官であったが、幼少時の生活は本当に悲惨だった。“賊軍”となった会津藩士の柴家は、懲罰とも思える斗南藩への移住で貧乏生活を余儀なくされていた。極寒の地で飢餓にも苦しむ有様だったから、毎日の食事だって“お粗末”としか言うほかない。
ある日、柴五郎少年は“しぶしぶ”であったが、知り合いの猟師が撃ち殺した犬を食べる破目になった。しかし、いくら空腹とはいえ、“野良犬の肉”じゃ気持ちが悪い。しかも、適当な調味料が無かったから、塩で犬肉を煮込むことになったという。柴少年は主食不足の補助になると自分に言い聞かせるが、やはり咽(のど)に通らない。すると、この様子を見た父親は、吐き気を催す息子を叱咤する。
武士の子たることを忘れしか。戦場にありて兵糧なければ、犬猫なりともこれを喰らいて闘うものぞ。ことに今回は賊軍に追われて辺地にきたれるなり。会津の武士ども餓死して果てたるよと、薩長の下郎どもに笑われるのは、のちの世までの恥辱なり。ここは戦場ぞ、会津の国辱雪ぐまでは戦場なるぞ。(石光真清・編著『ある明治人の記録』中央公論新社、1971年、p.64.)
令和の小学生なら驚くというより、意味が分からないだろう。普通の一般家庭だと、息子や娘は「ママ、お昼はビッグ・マックかシーフード・ピザにして!」とねだったりする。ベトナム戦争で従軍した海兵隊員だって、パック詰めの鶏肉や豚肉が入った携帯食(ration)に加え、ユナイテッド・フルーツ社のパイナップル缶詰を喰っていたくらいだから、狗肉(くにく)のベトナム料理がランチだと暴動が起きてしまうだろう。
明治の頃だと、秋山好古や副島種臣のような豪傑がいて、「質実剛健」を体現するような国民が少なくなかった。武士の家庭だと料理に文句を垂れる子供は両親から厳しく叱責され、「つべこべ言うんじゃない! それなら夕飯抜きにするぞ!」と脅されるのがオチである。そうじゃなくても、「生き恥を晒すくらいなら切腹しろ!」というのが、武家の教えであったから、役人や軍人になる武士の子は、公金横領や瀆職行為なんか恐ろしくて出来ない。昔、『逆・日本史』を書いた樋口清之が語っていたけど、彼が東京の大学へ進む時、祖母が伝家の宝刀を渡し、「男子の名を辱めるような事をしたら腹を切れ!」と命じたそうだ。








(左 : 秋山好古 / 副島種臣 / 西郷従道 / 右 : 山本権兵衛 )
ちなみに、大東亜戦争で日本が敗れた時、柴五郎大将は絶望感や焦燥感を抱いたのか、自決を図ったという。ただ、85歳という高齢であったから実行できなかった。しかし、その怪我が元で昭和20年12月13日に永眠することに。日露戦争で首相を務めた山本権兵衛大将も“やはり”国士といえる武士で、もう少しで“自決”するところだった。明治33年、山本首相は戦艦「三笠」を購入したかったが、帝国海軍の予算が尽きてしまったので、戦艦の発注が出来なかった。そこで、内務大臣だった西郷従道を訪ね、何かいい智慧がないのかと相談をもちかけてみた。すると、西郷は呵々(かか)と笑って答えた。
それは御国の大事ではないか。直ぐに注文しなさい。予算を流用して直ぐに金を渡しなさい。違憲ではあるが、今になって大切な建艦を見送るわけには参らぬ。もし違憲を追及されたら二人で二重橋の前で腹を切ろうじゃないか。多分、議会もゆるしてくれるだろう。二人が死んでも三笠が出来れば結構ではないか。(西郷従宏『評伝 西郷従道』芙蓉書房、昭和56年、p.304.)
日本は“質的”に変わってしまった。戦前の頃までは、国家は個人に優先し、“恥”を知る政治家も多かった。ところが、敗戦利得者が跋扈する昭和の後半には、“破廉恥漢”が総理大臣や高級官僚になっている。平成や令和の政治家で、自らの命を犠牲にしてまで祖国に殉じようとする奴がいるのか?
敗戦後、我が国は米国により陸軍や海軍を奪われ、貴族院と華族制度が廃止されたうえに、財閥解体という折檻まで受けた。進歩的文化人や日教組は、「戦後民主主義」とやらを絶賛したが、選ばれた国会議員や地方議員は、社会主義とか共産主義に憧れた左翼分子、あるいは地元に銭を配ることで人気を得ようとする利権屋だった。戦後復興と経済成長を経ると、衆議院議員は“国益”を蔑ろにする“支持母体の代理人”と化したし、参議院に至っては衆議院に落選した者の救済機関か、スポーツ選手や藝人の再就職先になっている。
本来、明治の日本が目指した「デモクラシー」は、英国型の混交政体(mixed constitution)であった。イングランド王国の統治形態を模範とすれば、国家元首が天皇陛下で、上院は世襲貴族、すなわち大名クラスの重鎮で構成され、下院議員は下級であっても武士階級の士族を主体とせねばならない。イングランド史を学んだ者なら気づくと思うが、日本の大学教授という種族は、英語を習得しても、日本語の感覚や日本の文化に疎いから、奇妙で的外れな訳語を用いたりする。
 (左 / フレデリック・W・メイトランド)
(左 / フレデリック・W・メイトランド) 例えば、フレデリック・W・メイトランド(Frederic William Maitland)の名著『The Constitutional History of England(イングランド國體史)』を和訳した小山貞夫は、「House of Commons」を「庶民院」と訳していた。(F.W.メイトランド『イングランド憲法史』小山貞夫 訳、創文社、1981年pp. 231, 243, 317, 318.を参照。) なるほど、「commons」は大抵の場合、「平民」とか「庶民」を意味するが、英国の政治制度で使われる用語となれば話は別だ。下院議員とは「共同体(communes)」から選ばれた「代理人」であり、元々は準貴族たる騎士が選ばれていた。(John Edward Austin Jolliffe, The Constitutional History of Medieval England : From the English Settlement to 1485, London : Adam & Charles Black, 1937, p.328.)
象牙の塔に住む教授はともかく、専門家でない日本人が「庶民」という言葉を聞けば、「江戸の庶民」とかを想像してしまうだろう。一般的に、「庶民」とは商人や職人、農夫とか猟師などの平民(国民 / 領民)を指す。「百姓」だって「万民」じゃなく、主に「農民」を指す言葉だろう。それゆえ、「庶民」の中に代官や町奉行、与力、同心、直参旗本の武士などを含めたら何となくおかしい。
西洋史を専攻する学者の間では、「庶民院」という訳語が定着している。だが、一般国民にとったら「士族院」と訳した方が適切だ。令和の日本だと、麻生家や岸田家のお坊ちゃんでも“庶民的”な姿を見せるが、階級社会のイングランドでは、「紳士・上層中流階級」と「労働者階級」とでは、様々な面で違っている。
例えば、酒を飲む時でも、“ホライトカラー(専門職や管理職)”が行くパブと“ブルーカラー(筋肉労働者)”が集まるパブは別個である。ちなみに、中流階級のイギリス人でワインを自宅で嗜(たしな)む者は裕福な者くらいで、1950年代か60年代に「ビストロ(bistros)」が英国で流行ったから、段々と普通の中流階級が呑むようになったらしい。(ジーリー・クーパー『クラース』渡部昇一訳、サンケイ出版、昭和59年、pp.341-342.) 一方、労働者の方は赤提灯みたいな居酒屋で、安っぽい「ジン(gin)」や「密造酒(hooch)」みたいな代物を注文する。彼らの自宅(or長屋)には「ワインセラー」といった御洒落な部屋は無いから、雑貨店でバドワイザーを買うくらい。休日になると仲間と集まり、一緒にビールをガブ飲みして、サッカー観戦に熱狂するのが定番だ。
例えば、酒を飲む時でも、“ホライトカラー(専門職や管理職)”が行くパブと“ブルーカラー(筋肉労働者)”が集まるパブは別個である。ちなみに、中流階級のイギリス人でワインを自宅で嗜(たしな)む者は裕福な者くらいで、1950年代か60年代に「ビストロ(bistros)」が英国で流行ったから、段々と普通の中流階級が呑むようになったらしい。(ジーリー・クーパー『クラース』渡部昇一訳、サンケイ出版、昭和59年、pp.341-342.) 一方、労働者の方は赤提灯みたいな居酒屋で、安っぽい「ジン(gin)」や「密造酒(hooch)」みたいな代物を注文する。彼らの自宅(or長屋)には「ワインセラー」といった御洒落な部屋は無いから、雑貨店でバドワイザーを買うくらい。休日になると仲間と集まり、一緒にビールをガブ飲みして、サッカー観戦に熱狂するのが定番だ。
話を戻す。中世のイングランドで「議会(特に下院)」に招集される非貴族といえば、大半が騎士階級の血筋に連なる紳士(gentry)か地主階級の生まれである郷士(squire)ときている。イングランドの“庶民”が連想する“士族”は、パブリック・スクールやマナー・ハウスで育った教養人。熱湯風呂で“ウケ”を狙う「たけけし軍団」の「そのまんま東」とか、ビキニ姿で貧素な肉体を晒していた「謝蓮舫」なんかが「士族院議員」に選ばれることはない。(蓮舫の写真集を買った奴は、いったいどんな神経をしているのか?) もし、ヴィクトリア女王が日本の「国会議員」を目にしたら、眉を顰めてしまい、側近のメルボルン卿(Lord Melbourne, William Lamb)に「あの東洋人は何者か?]と御下問なさるだろう。たぶん、ウェリントン公爵(1st Duke Wellington, Arthur Wellesley)だと鼻で笑って沈黙するんだろうなぁ~。








(左 : 謝蓮舫 / メルボルン卿 / ウェリントン公爵 / 右 : ヴィクトリア女王)
とにかく、イングランドの政界で「士族院」に選ばれるのは、紳士や郷士の旦那衆で、藝人や左翼がノーリッヂとかシェフィールド、ダービーといった共同体の“代表”に鳴ることはない。著名な選出議員と言えば、チューダー朝からスチュアート朝にかけて活躍したエドワード・クック卿(Sir Edward Coke)が挙げられる。偉大なる法学者であったエドワード卿は、民訴裁判所や王座裁判所の首席判事、ならびに枢密院顧問官として知られているが、士族院の議員になったこともある。「国士」と呼べる議員は他にもいて、チャールズ1世に諫言すべく、寵臣のバッキンガム公爵を批判したジョン・エリオット卿(Sir John Eliot)も有名だ。同時代の議員としては、大法官や民訴裁判所の首席判事を務めたジョン・フィンチ卿(Sir John Finch)が思い出される。フィンチは士族院議長(Speaker of the House)にもなっていた。








(左 : エドワード・クック卿 / ジョン・エリオット卿 / ジョン・フィンチ卿 / 右 : バーリー卿ウィリアム・セシル )
名門貴族の子孫も士族院議員になっており、女王エリザベス1世に仕えたバーリー卿(Lord Burghley)ウィリアム・セシル(William Cecil)には、二番目の妻ミルドレッド・クックとの間にできた次男のロバート・セシル(Robert Cecil)がいた。この傴僂(せむし)息子は枢密院顧問官や国務大臣に就く前、士族院議員を務めたことがある。エリザベス女王から「余のピグミー(my pygmy)」、ジェイムズ1世からは「余のリトル・ビーグル(my little beagle)」とからかわれたけど、有能だったので初代ソールズベリ伯爵(1st Earl of Salisbury)になっていた。ロバートには異母兄弟がいて、バーリー卿の長男であるトマス・セシル卿(Sir Thomas Cecil)も、エリザベス治世下で士族院議員になっている。








( 左 : ロバート・セシル / トマス・セシル卿 / ジェイムズ・セシル / 右 : ジェイムズブラウンロー・ウィリアム・ガスコイン・セシル )
初代エクスター伯爵(Earl of Exter)となった、このトマス卿の息子も世襲議員になっていて、次男のリチャード・セシル卿(Sir Richard Cecil)は士族院議員となったし、セシル家の子孫は次々と議員や官僚になっていた。初代ソールズベリ侯爵(1st Marquess of Salisbury)となったジェイムズ・セシル(James Cecil)も下院議員になったが、後に父親の跡を継いで上院議員になっている。第二代ソールズベリ侯爵のジェイムズブラウンロー・ウィリアム・ガスコイン・セシル(James Brownlow William Gascoyne-Cecil)も議員に選ばれ、三代目のロバート・アーサー・タルボット(Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil)、四代目のジェイムズ・エドワード・ヒューバート(James Edward Hubert Gascoyne-Cecil)、五代目のロバート・アーサー・ジェイムズ(Robert Arthur James Gascoyne-Cecil)などが士族院の議席に就いている。








(左 : リチャード・セシル卿 / ロバート・アーサー・タルボット / ジェイムズ・エドワード・ヒューバート / 右 : ロバート・アーサー・ジェイムズ )
日本でも有名なホイッグ党のロバート・ウォルポール卿(Sir Robert Walpole)は、地方紳士で士族院議員だった父ロバート・ウォルポールの三男として生まれた。この息子は英国のエリートらしく、イートン校とケムンブリッジ大学を経て士族院議員となり、首相や大蔵卿を務めたあと、初代オルフォート伯爵(1st Earl of Orford)に叙せられた。初代チャタム伯爵(1st Earl of Chatham)となったウィリアム・ピット(William Pitt)も世襲議員で、父のロバート(Robert Pitt)は士族院議員だったが、祖父のトマス・ピット(Thomas Pitt)はマドラス管区長(President of Fort St. George, Madras)だ。首相になったウィリアム・ピットには、同姓同名の息子がいて、「小ヒット」と呼ばれたウィリアム・ピット(William Pitt the Younger)も英国の首相になった。国王ジョージ3世の指名というか、一種の賭けで、王国の宰相になった訳だが、僅か24歳で首相に就任じゃ、色々な陰口があっても当然だ。




(左 : ロバート・ウォルポール卿 / ウィリアム・ピット / 「小ピット」のウィリアム・ピット / 右 :トマス・ピット)



昔、上智大学教授だった渡部昇一先生が述べていたけど、イングランドが繁栄したのは「デモクラシー」じゃなく、「ジェントルマンによる統治」だったからという指摘があった。第20世紀後半のイングランドが大国(super power)の地位から転落し、「英国病」に悩む程の醜態を晒したのは、大衆支配の国家になったからだ。ヴィクトリア朝の英国を知る者には堪えられないが、国内では労働党が台頭し、オックスフォードやケンブリッジ、ロンドン大学などでは、ハロルド・ラスキ(Harold Joseph Laski)やジェラルド・アラン・コーエン(Gerald Allan Cohen)、エリック・ホブズバウム(Eric John Ernest Hobsbawm)のようなユダヤ人学者や、クリストファー・ヒル(John Edward Christopher Hill)みたいなマルキストが溢れていた。こんな有様だから、プラトンが嫌った「カキストクラシー(kakistocracy / 劣悪な者による支配)」が固定化しても当然だ。近世までの西歐では、君主政と貴族政(aristocracy / 優秀な者による支配)が理想の政体となっていた。それゆえ、新旧の労働党や隠れ共産主義者が台頭する政界なんて論外。目眩がするほど恐ろしかった。








(左 : ハロルド・ラスキ / ジェラルド・アラン・コーエン / エリック・ホブズバウム / 右 : クリストファー・ヒル )
確かに、現在のイングランドの下院は、まさしく「庶民院」に相応しい。何しろ、労働組合上がりの“族議員”や金融業者の手先となった売国奴、低能丸出しの平民議員、帰化国民のパキ人やインド人の親を持つ2世や3世が当選して大臣や首相になっている。例えば、有色人種のリシ・スナク(Rishi Sunak)が首相となり、パキスタン系のサディク・カーン(Sadiq Khan)がロンドン市長、アフリカ系のキース・ヴァズ(Nigel Keith Anthony Standish Vaz)がヨーロッパ担当大臣になっているんだから、パブリック・スクール卒のイギリス人が聞いたらビックリ仰天だ。さらに、サイーダ・ワルシ(Sayeeda Hussain Warsi)やビク・パレク(Bhiku Parekh)のように男爵位(Baron /Broness)を授かったアジア系貴族院議員も居るんだから世も末である。




( 左 : サディク・カーン / キース・ヴァズ / サイーダ・ワルシ / 右 : ビク・パレク )




( 左 : サディク・カーン / キース・ヴァズ / サイーダ・ワルシ / 右 : ビク・パレク )
脱線したので話を戻す。そもそも、なぜイングランドで紳士や郷士の起源になる騎士階級が勃興したのかと言えば、それは国王が大貴族の野心を排除したり牽制するためであった。有力な公爵とか伯爵などは時折、チャンスがあれば王位の簒奪やクーデタ並みの叛乱を企てたりするから、棟梁としての国王は安心できない。だから、王族への野心を持たない準貴族、とりわけ君主と王国に心からの忠誠を誓う騎士は貴重だ。中にはロクデナシも混じっているけど、世襲貴族よりも数が多いから、有能な紳士が自然と浮かび上がってくる。所謂、「嚢中之錐(のうちゅうのキリ)」というやつだ。王国全体を効率的に支配したい国王からすれば、血筋だけで公爵や伯爵になったボンクラ息子より、文武両道に秀でた紳士を用いる方が、よっぽど賢明である。実際、ヘンリー1世やヘンリー2世は、王座の裁判権を強化すると共に、各地の「州長官(sheriff)」とか「巡回裁判官(itinerant justice)」に騎士や地方の名士を充(あ)てていた。
英国の陪審員裁判も中世の頃に確立された司法制度で、地方の領地で訴訟沙汰が起きれば、先ず四人の騎士が選ばれ、その者達が12名の騎士を選出して問題の審議に取り組んでいたのである。また、こうした地方行政官の騎士は、当時の“中央政府”とも呼べる「王の法廷(Curia regis)」に招聘され、重要な法律や政治議論に加わるよう命じられた。ただし、最初は傍観者のような立場であったが、徐々に戦争や課税の議論に加わるようになり、しまいには王様の方針に異議を唱えることも。こうして下院の騎士達は国政を左右するような勢力になっていった。士族院の起源や発展については、メイトランドの著作やウィリアム・スタッブス(William Stubbs)の『The Constitutional History of England』、およびスタンリー・B・クライムズ(Stanley Bertram Chrimes)の『An Introduction to Administrative History of Medieval England』を読むと、複雑な英国の憲政史や行政史がよく解る。
とにかく、ノルマン人に征服されたイングランドでは、封建貴族を率いた国王が、自らの権力を強化し、中央集権で政治を行うという有様になったが、それが幸運な逆説となって中流階級が栄えるデモクラシー的国家になっていた。“征服王”と呼ばれたウィリアム1世は1086年、ソールズベリに有力な土地保有者を集め、国王に対する忠誠を誓うよう命じた。(Edward Shepherd Creasy, The Rise and Progress of the Englsih Constitution, London : Richard Bentley, 1853,p.88.やJames Clarke Holt, ed. , Doomsday Studies, Suffolk : The Boydell Press, 1987, p.42.およびHenry Alfred Cronne, 'The Salisbury Oath', History, Vol. 19, Issue 75, 1934, p.250.を参照。)
ハロルド王を倒し、新たな支配者となったノルマンディー公爵が、ヨーロッパにいる他の君主や領主と違う点は、封土を直接もらっている「直属受封者(tenants-in-chief)」だけでなく、その臣下となっていた「陪臣(sub-tenants)」にも国王への忠誠を誓わせていた方針にある。見方によっては高圧的な専制君主にも思えるが、封建制に特有な地方貴族の叛乱を防いだことでイングランド王国の安泰に貢献することになった。
「法案作成能力」じゃなく「信頼」と「知名度」が鍵となる選挙
「法案作成能力」じゃなく「信頼」と「知名度」が鍵となる選挙
封建制を基盤とする立憲君主政のイングランドで、なぜ平民の下院議員よりも紳士の士族院議員の方が良いのか、と言えば、それは「信頼」の点で勝っているからだ。基本的に民衆は“新奇なもの”や“異質な文化”、“見知らぬ他人”を無意識的に嫌う。そして、“身近”で“馴染みのあるもの”に安心感や好意を抱く。だから、日本でも自民党が長期的な“政権与党”になっている。“ブランド”を有する自民党は、金銭スキャンダルや浮気問題が発覚しても選挙に強く、“異質”な共産党や公明党は、一部の“マニア(赤色分子やカルト信者)”を除いて、全く人気がない。自民党が内部から腐敗し、売国奴が幹事長や官房長官になっても野党に転落しなかったのは、全国各地の一般国民に、その党名と信頼が浸透していたからだ。
巷のオッちゃんやオバちゃん、藝人の色恋沙汰に夢中な姉ちゃん兄ちゃん、仕事で忙しいお父ちゃんは、政党や候補者の公約なんかに興味を示さない。「名前を聞いたことがある」という理由だけで投票してしまうのだ。横山ノックや青島幸男、橋下徹、小池百合子、三原順子、中条きよし、今井絵理子に統治能力なんて微塵も無いし、谷亮子やアントニオ猪木なんかはバラエティー番組のゲストにしか適さない。
自民党から出馬すれば、昼行灯(ひるあんどん)の新人候補や官僚上がりの落下傘候補でも、あるいはパンティー泥棒の世襲議員でも当選(再選)するし、たとえ小選挙区で落選しても、比例復活で当選する可能性が高くなる。一方、弱小政党だと初当選は困難だ。どんなに優秀な人物でも、“馴染み”の無い政党からの出馬となれば絶望的となるだろう。肝心な選挙資金は集まらないし、メディアからの取材も無い。熱心な友人やボランティアが手弁当で頑張っても、ほぼ落選という結果に終わってしまうのが定番だ。なぜなら、どこからともなく現れた“無名の新人”は、信頼できない“よそ者”であるから。彼らが駅前や商店街でいくら叫んでも、大衆はその主張に耳を貸さず、しぶしぶながらでも“常連”の世襲議員に投票する。これが冷酷な現実における選挙の実態だ。
選挙に挑む者が苦労するのは、「名前」を売って「信用」を得ることにある。それゆえ、立候補者は法案作成能力よりも、“どぶ板行脚”に専念し、街角を歩いて大声で名前を連呼するだけ。日本の舵取りを担う「政務官」を選ぶ「国政」なのに、その主張は「地方議員」の「利益誘導」なんだから、「国家の命運は誰が担っているんだ?」と訊きたくなる。こんな連中なら、地元の殿様や家老、名家の士族、庄屋さんが、衆参の国会議員や県知事、市議会議員になった方がいい。親子代々、民衆から尊敬される世襲の名士なら、ビラ配りや運動会に時間と資金を使わなくても済む。それに、家門の誇りを大切にする士族なら、あからさまな横領はしないし、皇室や国土を外人に売り渡す卑劣漢になる危険性も比較的少ない。まぁ、德川家や島津家、毛利家、伊達家の御曹司でも、ハニー・トラップに引っかかることもあろうが、「末代までの恥」を知っているから、潔く辞職して蟄居するか、腹を切って詫びることになるだろう。
今のところ、日本はデモクラシーという政体を変えないから、岸田文雄が退陣しても、次にやって来るのは茂木敏充とか河野太郎、林芳正、小泉進次郎といった“残り滓(かす)”くらいだ。日本人は自分自身の生活や家族の生命に危機が訪れるまで、現状を変えることはない。第三次世界大戦が勃発するか、自宅に巡航ミサイル、あるいは戦術核ミサイルが落ちてくれば、瞬時に「民衆政治じゃ駄目だ!」と気づくだろう。そこまで酷くなくても、我が子が北鮮に拉致されたり、大量の難民や移民が自宅周辺に住み着けば、ちょっとくらいは政治的関心を抱くようになるはずだ。悲しいけど、日本人は実際に“悲惨な出不幸”を経験しないと明確に解らない。日本人が目覚める時は、国家沈没の1週間前かも知れないよ。
人気ブログランキング

















